
2025.05.19
課題解決の質を高める「場づくり」の力:「ワークショップデザイナー」の学びから
電通デジタルは、事業開発やサービスデザイン・UXデザインにおいて、多様な関係者との『共創』を通じて最適な解を導き出すことを重視しています。
その手法の一つがワークショップであり、当社にはコミュニケーションの場づくりの専門家である「ワークショップデザイナー」が複数在籍しています。
今回は、青山学院大学のワークショップデザイナー育成プログラムを修了した社員の経験をもとに、ワークショップデザイナーとしての専門性を高めることの意義や面白さ、また電通デジタルの業務での生かし方について紹介します。
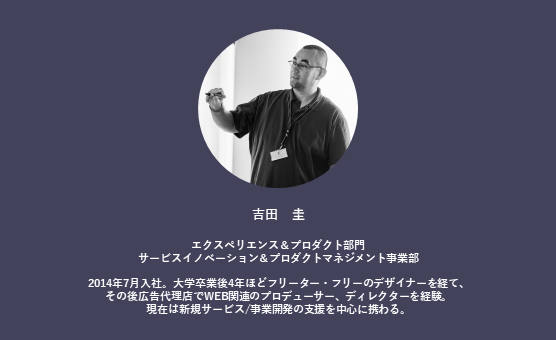
ワークショップデザイナー(通称:WSD)とは、「コミュニケーションの場づくりの専門家」。
コミュニケーションを基盤とした知識や技能を活用する参加体験型活動プログラムをデザインする専門職です。
この資格を取得しようと思ったきっかけは何でしょうか?
吉田(以下Y):資格を取りたいというよりは、ワークショップについてもっと学びたい、スキルや思考を深めたい、という気持ちがあるなかで、電通デジタルの前身の電通イーマーケティングワンでワークショップ形式の仕事をする機会がいくつかあり、自分自身にとってワークショップという手法がフィットしたため興味を持ちました。

カリキュラムはどのような構成ですか?
Y :前半、後半で区分され、前半は大人向けワークショップの企画~実施まで、後半は子ども向けワークショップの企画~実施までの内容です。
それぞれ前半、後半で違うチーム(5人)が組まれます。
※カリキュラム内容は2015年当時のものです
面白かった、印象に残った授業・カリキュラムはありますか?
苅宿先生(※1)の講義が面白かったです。
自己紹介から他己紹介を2回繰り返し、最終的に、他人が伝え聞いたものが自分に戻ってくるという15分程度のワークでした。
自分が言いたいことが抜け落ちていたり、ニュアンスが違ったりした自己紹介になって自分の紹介を他人から聞くことになります(他己紹介)。 実はこのカリキュラムには、「人のうわさの仕組みを体感する」という裏の目的があったことを知り、コミュニケーションのずれを体感する新しい学びとなりました。
劇作家の平田オリザ先生(※2)の講義も印象的でした。
世の中で、(特にビジネスシーンのにおいて)会議参加者は必ず発言をしなければならない(バリューを出さなければならい)と言われることがあると思いますが、演劇では話さないことが重要な価値となり得るとのことでした。
例えば演劇において教室の授業のシーンで、寝ている生徒がいると、それを起点としてストーリーが展開したりします。
その観点から考えた時に、「黙っているから意味がない、価値がない」という論理は演劇などいわゆる芸術の分野では逆転するとのことでした。
個人的な意見としては、会議中に発言したり議事録をとったりしなくても、よく話を聞き思考しそのプロジェクトの中で誰かの発言にひと言コメントするだけでも意味も価値もあるのではないかと考えたりします。
ですので、発言のタイミングやアクションはいつでもよいと思っています。それこそがダイバーシティ、多様性だと思います。
なかなかそうもいかない現状もありますが、心持ちとしてはそう持っております。
※1 青山学院大学 社会情報学部 教授 苅宿俊文氏
青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラム
※2 わかりあえないことから コミュニケーション能力とは何か(講談社現代新書、平田オリザ著)
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000210663
WSDのスキルは、電通デジタルでの業務においてどのような価値をもたらしていますか。
Y:ワークショップの基本を理解できて、プロジェクトでワークショップを実施する際に役に立っていると感じています。3か月濃密に学ぶことができ、思考を深めることができました。
これまでは、仕事上でのワークショップはなんとなくの暗黙知のような、まずはアイスブレイク~発散~収束のような、こうやるものと疑うことなく行ってきましたが、資格取得後にはプログラムデザインやファシリテーションなどに目的を持って検討できる様になったと思います。
現在の業務にも、この学びやマインドがよきものとして生きていると思います。
WSDの受講者には多様なバックグラウンドの方々がいらっしゃるそうですが、そのような方々との協働経験からはどのような学びが得られましたか?
Y :さまざまな方がいて、ビジネスパーソンのほか、演劇をされている方、看護師さん、自衛隊の方などがいました。看護師さんについては、災害時オペレーション教育のために、このワークショップが活用できるのでは?という目的で参加されていました。
自衛隊の方は、東日本大震災の支援に行き、人の命は自分1人では1人だけしか救えないことを体感し、このままでは奥様や子どもなど家族全員を守ることができないと思ったそうです。
そこで、地域のコミュニティ機能として地域住民とともに防災や救助などを実現するために、このワークショップを学びに来ていました。
そのような異分野の参加者の方たちと、授業終わりに皆で近所の居酒屋などでコミュニケーションを図り、色々な考え方を知ることができ、仲間も増えました。

この資格取得にともなうカリキュラム、グループワークを通して、吉田氏は受講者同士で色々な意見交換を行い、多様な考え方を知ることができたといいます。
多様なバックグラウンドを持つ受講者との意見交換や関係構築の経験は、まさに電通デジタルがビジネス・UXデザインの課題解決において重視する『多様な視点の統合』と『共創による価値創造』のプロセスそのものです。
WSDの体系的な学びにより、『なぜこのプログラムなのか』『このファシリテーションで何を目指すのか』といった明確な意図を持ってワークショップを戦略的に設計・運営する力が向上します。
電通デジタルでは、このように暗黙知を形式知・実践知へと高めた専門性を活かし、クライアント企業との共創ワークショップや社内プロジェクトにおいて、参加者のポテンシャルを最大限に引き出す『場』をデザインしています。
これにより、単なるアイデア出しに留まらず、関係者の深い合意形成や成果に直結する質の高いアウトプットを生み出すことに貢献しています。
渋井尊之
共生社会推進グループ
電通デジタルにて、企業へのWebプロモーションの企画提案、Webコンテンツ制作やサイト構築/改善、運用ディレクション業務、アカウント業務まで幅広く経験。2023年よりDEI推進の部署へ異動、2025年より障害者の雇用支援のために従事している。
※所属は記事公開当時のものです。

濱藤柚香子
エクスペリエンス&プロダクト部門
2020年に電通デジタルに入社。ユーザー起点での画面設計やUXリサーチ、ワークショップ設計・運営業務など幅広い支援業務に従事。青山学院大学履修証明プログラム修了ワークショップデザイナー(2024年修了)
※所属は記事公開当時のものです。
RELATED REPORT


